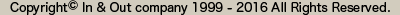|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
|
|
◇〜シネマ(&ブック)・キャッチ! NO.6〜 『“心”を移植する産業』Text by Gochy! 12日、日本に先駆け米国で公開された映画『FINAL FANTASY』(監督・坂口 博信)。日本人監督の作品が全米2000館以上で公開されるのは初の快挙らし い。日本では今秋「日本劇場」他で、全国ロードショーとなるわけだが、日 本人監督作品が「日本劇場」でかかるのもこれまた初めてのことだとか(劇 場名に「日本」がついていながら妙な気もするけど、要は日本劇場って興行 的に絶対的な成功が見込めるハリウッド・メジャー御用達の“箱”なのね)。 こんな初めてづくしが、すでにその高期待度を物語る本作。最大のウリは、 “感情”までもフルCGで表現したという「史上初のスーパーリアリスティッ クCG映像」。試写はまだ始まってないが、17分の特報フィルムを観た限りで は、確かにCGによる“肉体の表現”は、ほぼ完璧な域に達したと言っていい。 本当に写真のようなリアルさだ。早く全編が見たくてたまらないが、本プロ ジェクトのテーマである「心」の存在を映像で表現するという点については どうか。高水準ではあるが、まだまだ違和感があるというのが正直な感想だ。 ▼ どの程度の違和感かといえば、『A.I.』で生身の俳優がロボットを演じたよ りもっと強い「アンドロイド」感が漂う。生身の人間がアンドロイドを演じ るのと、“バーチャルアクトレス(アクター)”が人間を演じるのと、ちょ うど同じくらいの水準。同水準ってのもヘンな言い方だけどね。もしバーチャ ルアクターが人間の俳優並みの表現力(私は瞬きを含む目の表情と口元の表 現がポイントだと思う)を身につけたら、ハリウッド俳優はもうストライキ とか言ってる場合じゃないね(笑)。その『A.I.』だが、米国での成績はイ マイチの様だが、日本ではスピルバーグ監督が関連グッズの販売を日本だけ 認可したりと「アトム」を生んだ国ならではの盛り上がり。作品の方は「ロ ボットと人間の共生の果て」の一仮説として興味深かったし、ハーレイ君の 健気な演技とジュードのセクシー・クールぶりも○。しかし強烈な消化不良 感が残ったのも事実。なぜ、ハーレイ演じるヒューマノイド・ロボット(人 間型ロボット)は、あれほど強く「マミーに愛されたい」という感情を芽生 えさせたのか?劇中では7つのキーワードがインプットされることがきっか けとなっていたけれど、そのメカニズムは最後まで私にとっては謎のままだ。 ▼ そんな謎の解明に何らかのヒントを与えてくれそうな本が『未来のアトム』 (田近伸和著/アスキー刊/2857円)だ。取材・執筆に2年を費やし、大学、 政府、大手企業のロボット開発の最新動向や科学的・哲学的理論から、ヒュ ーマノイドの未来に迫った大著。ロボットに感情や個性が芽生えるメカニズ ムを解明するには、工学的アプローチだけでは限界があり、心脳問題や哲学 を含む「人間そのものの解明」がポイントだという視点が興味深い。ロボッ ト先進国の日本では、現在大別して2つのタイプのヒューマノイドの開発が 進行している。ホンダのアシモのような正確な作業を目的とした実用重視型 ロボットと、ソニーのSDR-3Xに代表される人間的動作や感情表現を目指すエ ンターテイメント型ロボットだ。『A.I.』で描かれていたのはこの2つの機 能に意志をプラスした最終型だ。冒頭で触れたバーチャルアクターにしても、 CG表現上のテクニックだけでなく、もし「意識」や「感情」が授けられたら どうなるか?自ら成長し、生殖し、繁殖する存在となったら?人造人間にヒ ューマンな「心」を移植する産業は、世界の未来にどんな影響を与えるだろ う。半世紀前の1949年、手塚治虫はアトムの原点である『メトロポリス』で こう問いかけていた。「おそらくいつか、人間は発達しすぎた科学のために 自らを滅ぼしてしまうのではないだろうか?」と。さて、我々の未来は…? |